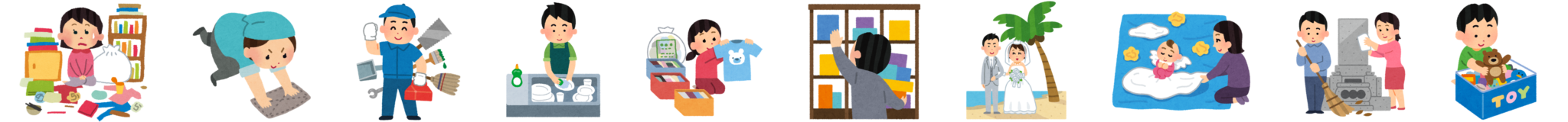井出と名乗るその男性が言うには、車はマンションの前に停めておけば問題ないとのことだった。全国的に建築物過密な日本で、そんなことってあるのか? と思っていたが、現地に着いて納得する——そして、驚いた。
湖を望めるように建てられたその集合住宅は、リゾートマンションというやつたっだ。記憶が確かなら、過去『リゾマン』と俗称されていた高級マンションだったはずだ。
諸々のアクセスも便利な立地条件なうえ、ここには来客用の駐車場まで完備されていた。
電話の受話口から聞こえてきた井出の声に、やや幼さすら感じていた揃江繕明は、車から降りてしばらく呆然と立ち尽くした。
「ヤングエグゼクティブとかって人なのかな?」
意味もよく知らない骨董品みたいな単語が口をついて出たことに一人吹き出す。
ふいに携帯電話の着信音が響いた。ポケットの中で震えているそれを引き抜いて通話ボタンを押す。
「はい、揃江です」
「ああ、やっぱりそうですか。どうも、井出です」
「やっぱり、とは?」
「マンションを見て下さい。上から少し下の右らへん」
言われた通りに見上げてみると、黄色いシャツを着た青年がバルコニーから身を乗り出してこちらに手を振っていた。遠目からでも、自分より若いだろうことがはっきりと見て取れる。
「どうも!」
「ああ……どうも」
おいおい、君は一体いつの年代を生きてるんだい?
繕明が引き気味で返事をしたあと、心情的なある種のタイミングを過ぎても井出は手を振り続けていた。
もしや、と思って手を振り返すと、
「今そっちに行きますから、待ってて下さい」
ようやく話が進展した。プツリと通話が切れる。
なんだか浮ついた雰囲気の人だな……。
奇妙なズレを感じながら、繕明は車のバックドアを開けて段ボール箱を取り出した。
「いやぁ、助かります。俺にとって揃江さんはまさに渡りに船ってやつでして——」
井出はロビーから自室までの間、繕明の一週間分はしゃべっていた。
建築関係の仕事に就いたのが四年前。今では現場監督を任されるまでに至り、おそらく永年固定の赴任先であるこの地に来て、見つけたのがこのマンションだったらしい。
「かなり安価だったんですよ。それこそ一括で買えるくらい」
「こんないいところなら、中古でもかなりしそうですけどね」
さりげなく値段を訊いてみる。
「別荘としての物件らしいんですが。まあ、諸々の問題があって——このくらいでしたね」
井出は指を四本立ててみせた。
400万!? 思わず目を瞠ってしまった繕明を尻目に、
「おはよう、トクさん。水道の方はどう?」
井出は繕明の背後に向けて投げかけた。
「ちょっと水圧が下がっとる。明日からゴールデンウィークか……、あとの3部屋がうまると、もうやばいかもな」
聞こえた野暮ったい声に振り返ると、50過ぎくらいおじさんがごま塩頭を掻き上げていた。
「ん? この兄ちゃんは?」
「ほら、この前言ってた。片づけ名人さん」
井出がタメ口で話しかけるそのトクさんにも「どうも」と、名刺を渡しておく。
「なるほど、兄ちゃん、どうかこいつにまともな部屋ってのをしっかり指導したってくれ」
去り際にトクさんから意味深な目を向けられた井出はくすぐったそうに笑った。
「それじゃあ、部屋こっちです」
歩き出してほどなく、井出はひとつのドアの前で立ち止まった。
「あの、驚かないで下さいね」
と、前置きしてきた。
ドアを開くと、まず廊下に脱ぎ散らかされている作業着とスーツが目についた。
井出の案内で廊下を進む。ドアというドアは全て開け放たれているみたいだ。
通り過ぎ様に覗いた和室は書斎として使っているらしく、でんっと構えた大きな机の上で、工業系の参考書が大量に折り重なり、書類のジャングルができ上がっていた。
廊下を抜けたところのリビングダイニングにはカーペットが敷かれていて、その上に車やメンズファッションの雑誌、筋トレ器具が散らばっている。
これぞリゾート、と言える申し分け程度のキッチンには、中身がなくなって積み重ねられたカップ麺と缶ビールの容器が、さながらビルのように林立していた。
それと、リビングの隣にはもう一つ和室があったが、そこにはペタンと万年床が敷き伸べてあるだけだった。シーツは色が染みこんでいて、触ると手がべとつきそうだ。
「とまぁ、こんな様でして」
恥ずかしそうに頭を掻く井出は、しおらしい声で言った。
「手始めに、いる物とゴミを分けましょう」
なにぶん量が多い。繕明はいる物を部屋の奥側に、ゴミは袋詰めにして玄関側に置くようにした。これなら必然的にゴミが廊下に集まる。最悪、なにか液体がこぼれ出たとしても、掃除の範囲を限定できる。臭いが残っても、カーペットよりはフローリングの方が断然除去しやすいうえに、染み抜きの必要もない。
いる物か否かを迷ってる物は、全部段ボールに詰め込んだ。
あらかたゴミがなくなってきた頃、使い捨て用の紙皿と割り箸が大量に出てきた。
「台所が小さいんで、食器洗いが面倒なんですよね。時々、買い置きしておいたのを忘れてて、また買っちゃったりして——」
「お皿は陶器でもプラスチックでもいいので、一枚は持つようにしてください。これ自体がゴミになってしまったんじゃ本末転倒ですから」
そう、必要以上の物の正体とは不必要な物で、すなわちゴミに化けてしまうのである。
しかし、さすがは工業系の人柄である。目的が定まり、繕明というカンフル剤が与えられた井出は実に能動的で、動き出すと止まらない様子だった。
ゴミがなくなると、驚くほどにリビングは空っぽになった。
いよいよ最後の大捕物である書斎で、井出が甲斐甲斐しく散らばった参考書を部屋の隅に積み上げていた。
すかさず繕明は指摘する。
「本は横に積んではダメです」
「え、どうしてですか?」
「せっかく持っていても、下の方の読まなくなってしまいますし、見栄えも悪い。本自体も、よれたりして壊れやすくなります。参考書ならば、なおのこと本棚を買って下さい」
「は、はい……」
「それと、書類整理が日常的に多いのなら、クリアファイルではなく引き出し式のファイルラックを——」
空が茜色に染まる頃、井出の部屋は見違えるほど綺麗になった。
「あとは、お一人でできそうですね」
「はい、ありがとうございました……」
再三、行動を指摘されたのが相当こたえたのか、井出は朝会った時と違ってげっそりとしていた。
「おお! こりゃあ凄え。部屋間違えたんかと思った」
無遠慮にずかずかと入ってきたトクさんが「感心感心」と言った。
「あっ、すいません。そこのゴミはすぐに捨てますんで」
繕明が井出の部屋の前に仮置きしたゴミ袋の群れのことを謝ると、
「いい、いい。ここのゴミの捨て方ってのはちょっと面倒なんだ。あれはこいつと俺でやるから——なっ?」
骨張った手に肩を叩かれた井出は、ほっとしたようにうなづいた。
「では、最後に」
繕明が向き直ると、「まだ何かあるのか?」と言いたげに井出は顔を上げた。
繕明は指を立てながら淡々と伝えた。
「風呂、トイレ、台所、そして寝室。つまり、家の中にある『食べる・寝る・清める』に割り当てられる部屋。その部屋の整理が疎かになっていると、人間は——ことに女性は生理的に一番嫌悪感を持ちますので、よくよく気をつかって下さい」
井出が複雑な表情に顔を歪ませる横で、トクさんがからからと笑った。
「じゃあ、私はこれで失礼しますので、井出さん今回の旅費は3千円くらいなので半額の千5百円を——」
「は?」
井出はきょとんとした顔をした。
「そうだ」
と、突然トクさんが大声を出して繕明と井出の間に割って入ってきた。
「ここの名物の展望室を観ないで帰るなんて気の毒だ。今ちょうどいい時間だから行ってきな」
「いや、あの——」
「大丈夫だよ。住人の俺が許可する」
繕明には質問をする権利も、拒否する権利もないようだった。
最上階の展望室は、幾分経年の劣化があるものの、掃除は行き届いていて小綺麗だった。
壁一面にはられた窓の向こう。田打ちも終わり、水が入った田園は湖面と一緒に夕さりの空を映し出し、湖の縁にそって細く伸びる街並みは、まるで空に浮いているようだ。
慣れない視線の高さと景色の壮麗さに、繕明は身体が床から数センチ浮き上がったような錯覚を覚えていると、
「いい眺めだろ?」
いつの間に隣にいたのか、トクさんが訊いてきた。
「ええ、とても平らに開けていて、気分が良くなります」
「さっき、あいつから聞いたよ。随分と灸を据えられたって」
「見たところ、あの部屋には洗濯機も置かれていませんでした。水圧云々のことも聞きましたし、リゾートマンションというのは、定住には向かないようですね」
「バブル期に好き勝手に乱立されたもんでよ、こんな物件が日本中にあるんだと。その内、建物ごと整理されちまうんじゃねぇかな」
言いながらトクさんはタバコに火をつけて一服した。
「今回、あいつにあんたを紹介したのは俺だ」
「なんで、それを隠したんですか?」
「女ができたんだと。だから部屋片づけんを手伝ってくれ頼まれたんだ。でも、知り合いの俺が手伝ったんじゃ、その場限りで学習しねぇだろ? だからと言って、業者に頼んだんじゃ、間で金が動くから途端に有り難みがなくなる。だったら一度、赤の他人からガツンと言ってもらった方が、あいつのためになんじゃねぇかと思ってな」
ある意味で過保護な話だ。
「ありがとな、これであいつも少しはマシになんだろう」
タバコを携帯灰皿でもみ消したトクさんは、無造作に取り出した財布から一万円を手渡してきた。
「まあ、ゆっくり景色を楽しんでから帰ってくれ。下であいつ待たしててな、急に食器買いに行くからついて来てくれって言い出しやがったんだ」
トクさんの背中を見送ったあと、繕明は窓の向こうに広がる景色に目を戻した。
「もし、ここが本当に不必要になって整理されてしまったら、この景色は二度と見れないんだろうなぁ」
紅く染まった光景が地平線と水平線の遙か先まで続いていた。