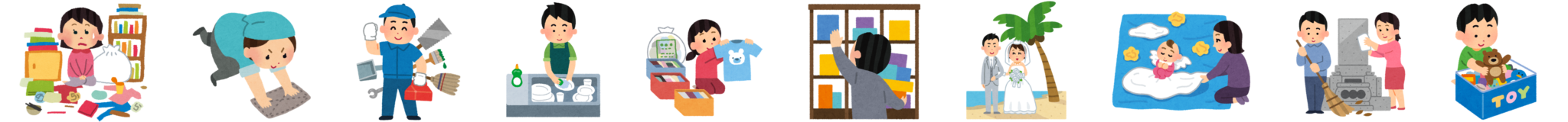「ふつー、俺を呼びつけるかね」
揃江繕明は溜め息を混ぜて呟いた。
ハンドルの上で交差させた腕のむこうでトラックが動きだす。大型エンジンの始動音は低く重く、フロントガラス越しにも腹に響いてきた。
トラックが前進すると、コンテナの陰からを青い空を小さな雲がぼかしていた。
〝久し振りだね、ヨッちゃん〟
数日前、突然掛かってきた電話はとても懐かしい声を聞かせてきた。
〝実はちょっと困っちゃっててさ。私の悪い癖が出ちゃって、そろそろやばいのよ〟
「つまり、結婚してからも変わってないってことだ」
今回は断ればよかった……。
独りごちながらそう思い、さらに気分が暗くなる。
ちくり!
「よせ! やめろ!」
繕明は怒鳴った。嫌なものが後頭部をかすめたからだ。身体中にうっすら汗がにじんで、シャツが肌にまとわりついて気持ち悪い。
「ああ、分かってる。分かってるよ! だから愛奈もみなまで言わなかったんだ!」
〝お願い。私を助けると思ってさ――ね?〟
繕明の従姉妹、木本愛奈(こもと えな)からの電話は、それだけ言うと、そこで、いきなり、一方的に切られた。
\\ピンポーン//
『綴木』と彫られた表札――明らかに玄人の手彫り――の前で、繕明はなよやかな電子音を聞いた。
繕明は綴木婦人宅をもう一度見上げ――今日何度目か分からない溜め息を吐いた。
「わぉ……」
爽やかな秋晴れを建材に使ったような、背景の青空に溶け込んでいきそうな、カリスマ建築家が遺憾なくその本領を発揮させたような住宅だった。
「下手な例えだろうけど、カットされたチョコレートケーキみたいだ」
この外観なら保険の外交員や冠婚葬祭の互助会勧誘員でも目が覚めて帰ってしまうだろう。
実は、繕明がインターホンを押せたのは到着して5分ほど経ってからだった。
いや、本当のところは10分は経っていた。
いいや、ここは正直に言ってしまおう。30分も綴木宅の前をうろうろしていたのだった。
このままだと近隣住民から不審者と見なされて通報されてしまうかもしれない、と勝手に持った危機感からインターホンを押した、と言った具合だった。
『はい、どちらさま?』
聞こえた声に驚いて肩がびくりと震えた。最近のインターホンのスピーカーはこんなに鮮明なのか、携帯電話より間近でしゃべられているみたいだ。
「……揃江です」
『よく1時間も尻込みできるね。迎えに行こうかと思ってたとこだよ』
そう責められるなり堅牢そうな門が自動で開いた。
繕明はかくんとうな垂れて足元に呟く。
「だったら、そうしてくれればいいじゃないか――」
『あはは、ごめんね~』
語尾に『♪』マークが付いてそうな言い方で返事をされる。
最近のインターホンはマイクの性能も高いらしい……。
「あれ、ちょっと老けてない?」
「ああ、今日だけで5年分は歳食ったよ」
言われるがままに数秒歩いて玄関に辿り着くと、愛奈がドアを開けて迎えてくれた。
浅栗色のロングボブ。ルームドレスにライトシアンのフリル付きカーディガンを羽織り、相変わらずの澄み切った笑顔はなんだか眩しく感じる。
「5年ねぇ~」
愛奈の目が意味深に細められる。
繕明はこの鬱屈とした気持ちを傍証する嫌な符合を自ら口にしてしまった。それを打ち消そうと話を切り出す。
「それで、どこ?」
「うん、こっち。2階なんだよね――ああ、靴のままでいいよ」
ふわふわと歩く愛奈のあとを付いて行きながら、見るとはなく内装を散見した。
実用的な採光窓のおかげで電灯はひとつとして点いていないのに、十分な明かりに満たされた空間。影まで絵になっている。諸所に置いてある家具は、調度品を意識した装飾が施されている物もあった。
階段を上がりながら見下ろした吹き抜けのリビングは、ホームパーティーにぴったりだろう。テレビ、カウチ、ソファーセットを据えても、3組のペアがダンスを楽しめるはずだ。各所に設けられたシーリングファンが絶えず屋内に気流を生み出していて心地好い。
まったく、趣味の良い旦那さんらしいや……。
「ここなんだけどね」
いつの間にか愛奈が立ち止まっていたので、繕明は危なくぶつかりそうになった。まあ、それも仕方ない。愛奈は廊下の途中で突然立ち止まったのだから。よく見ると壁と同じ色をしている引き戸があった。目の高さにプレートがあって『dress room』と筆記体で刻印されている。
繕明がつんのめっていると、愛奈が開いて振り向いた。
「あれなの――」
愛奈が指をさすその先に、家の雰囲気にはまったく似合っていない箪笥が〝でん〟と鎮座していた。下半分が古風な衣装箪笥になっていて、上半分は洋服を入れる観音開きだ。
繕明はその箪笥に見覚えがあった。
ちくり!
だからやめろって!
そう、もともと木本家にあった物だ。どうやら、花嫁道具としてもらったのだろう。今どき箪笥か……あの古き良き両親ならではの発想だな。
「それじゃあ、見てみますか――」
つかつかと靴底を鳴らして箪笥に近づいた繕明は、遠慮無くその観音開きの戸を開け放った。
途端に数本のネクタイが百花繚乱飛び出してきて床に散らばった。一緒にくっついているネクタイピンがフローリングにぶつかってカチャカチャと音を立てる。そのにぎやかしにカフスボタンも加わっている。顔を上げると、かさ張ったスーツやドレスが膨らんで箪笥から迫り出してきていた。
「よくこれだけ出っ張らせられるもんだな?」
「言ったでしょう、悪い癖が出たって。片づけが面倒になるとここに押し込むようになっちゃってて、なんとかして欲しいの。こんなのあの人が見たら卒倒しちゃうもん」
だったら自力でなんとかしなさい。思いっ切りそう言ってやりたかった。が、そうは言ってやれない。
「なにか箱とかないかな? こう――間仕切りされているのとか――」
「ああ、この間来たお客さんからもらったクッキーの箱がそうだったかも」
愛奈が持ってきた箱に、繕明はネクタイをしまい始めた。二つ折りにしてからくるくると巻いていく。
「こうすればシワになりにくいし、場所も取らない。ネクタイピンとカフスボタンも、隣に並べておけば色合せもし易い――な?」
しまい終わった箱を愛奈に向けた。
「ほんとだ」
並んだチョコレートを見る子供のような笑顔でそう答える。
胸につっかえる物を感じている繕明は愛奈の顔から箪笥に目を戻した。
「あとの洋服はシワだらけて着れたもんじゃないから、一度クリーニングに出した方がいい。その間この中は空っぽになるから、どこにどうしまうか考えられるだろ?」
「うん、そうだね。今日中に電話しとく」
取りあえず中の物を全部出していった。
「それにしても、二人暮らしにしては物が多いな」
「あの人にも、消費癖っていう悪い癖があるのよ」
夫婦揃って……。
洋服以外にも、両親からもらったらしいネックレスや指輪なども出てきた。
「あっ!」
愛奈が声を上げて一枚の服を取り上げた。
「こんなところにあったんだ。お母さんにもらってから忘れてた」
それは産着だった。
気の早い話だ。
そう思った時、愛奈が愛おしそうにお腹をなでた。
途端、繕明は自分の内側になにかが〝ストンッ〟と収まるのを感じた。秋風が胸を吹き抜けた気がした――なぜか、自然と口元がほころんだ。
その時、玄関の扉が開く音がした。
「ただいま~、愛奈。今帰ったぞ」
愛奈の夫の声だ。確か清司とか言う名前だったはず――って!
「お、おい! まずいだろ、これ――」
「なにが?」
愛奈はきょとんとした顔でうろたえる繕明を見ている。
「なにがって……親戚とは言え、新妻と男が二人きりなんて、変に勘繰られても仕方ないじゃないか」
無意識に声をひそめた繕明は愛奈に笑われた。
「大丈夫だよ。あの人には言ってあるから」
寒いものにさっと首筋をなでられた気がした。
「言ってある……? なにを?」
「さぁ、なんでしょう?」
ほどなくして、
「愛奈ぁ、ここか?」
声の主が顔を出した。デザイン性の高い眼鏡にも飾られない端整な顔形は、繕明とは似ても似つかない。グリーンのカッターシャツをタックインしたスラックス姿は、休日を楽しむためのパパその物だ。
「ああ、あなたが片づけ名人の揃江さんですか?」
「は、はい、揃江繕明です。よろしく」
反射的に出してしまった名刺が、相手の物と交換される。
[ ユーロポート株式会社 流通管理部 課長 綴木清司 ]
「旅先片づけ請負人――なるほど、これがあの有名な名刺ですか」
「いやぁ、有名ってほどでは」
「謙遜することはありませんよ。ときには企業からの依頼もあるとか、いろいろ愛奈から聞いています」
「はあ、それはどうも――」
などと着地点のつかめない応酬で数分を過ごしたあと、繕明は昼食に誘われた。実に気持ちよく話を進める男だ。気構えもなく「はい」と了承してしまうところだった。
失礼にならないよう、細心の注意をはらってお断りした繕明は、綴木夫妻に門の所まで見送られた。
「では、失礼します」
車のドアを開けた時、愛奈がすすっと顔を寄せてきた。
「あの人はね、ヨッちゃんみたいに器用に生きれないの。私がいないとダメなんだよ」
ちくり!
もういいって……。
「綴木さん。お幸せに」
「うん! またね、ヨッちゃん」
清司に会釈した繕明は車のタイヤを大通りに向けた。
国道に入り、さっさと高速に乗ろうとギアを3速に上げる。と同時に車の流れが弱まった。
なんとか停車したが、危なく接触事故だ。目の前に朝見たのと同じ飛脚のトラックが止まっている。
ややあって、トラックが少し前進した。コンテナの陰から雲のないすっきりとした青空が顔を出す。
『愛奈、俺と付き合ってくれないか?』
『ダメ!』
あの時、愛奈は本当に間髪入れずに断ってきた。しかも、割と強めの口調で――。
5年前、あの箪笥の前で告白した時を、繕明はちゃんと思い出してみた。
もう、ちくりとは来なかった。
「そっか――。俺、やっと次の恋ができるんだ」
綴木夫妻の幸せそうな顔と産着。
そんなことを青空の中に思い浮かべていると、目の前のトラックがスムーズに進み始めた。