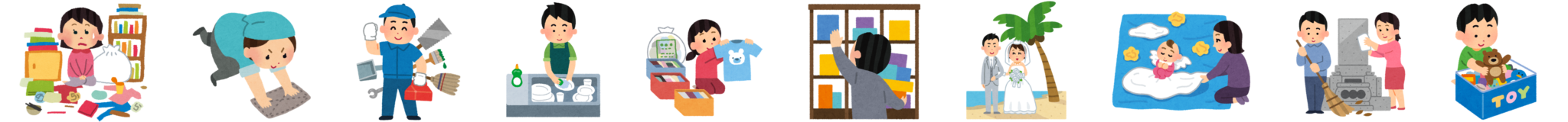オフィスの給湯ブースに芳ばしい煙が立ち上る。トップバリューの『レギュラーコーヒー』は悪くない。酸味がなく、目の覚める苦味と香りが味わえる。安価にしてその品質は、買い手にとって実に叶った釣合い方をしている。
ささやかな休憩時間のひととき。
繕明がドリップ口から盛り上がる珈琲アロマを楽しんでいると――。
「この馬鹿野郎!!」
まさに青天の霹靂。静謐なオフィスに怒罵が轟いた。
拍子に注いでいたお湯がぶれて、ドリップ内のコーヒーが跳ねる。幸い、スーツに飛沫がつかなかったので、繕明はほっと胸をなで下ろした。
声のした方に首を巡らせると、オフィスにいる全員の視線がリーダーのデスクに集中していた。
デスクの前には、ばつが悪い顔をした青年が立ち尽くしていて、叱責から逃れるように目を足元に泳がせている。
リーダーはろくに手入れもしていない蓬髪を、神経質にばりばりと掻きむしった。
「このあいだも、その前からも、再三注意したところがまた間違ってんじゃないか!!」
言いながらリーダーはもう一方の手に持った書類で空気を乱暴にかき混ぜる。
「す――すいません……」
青年は謝罪を述べて、萎れたもやしみたく深々と頭を下げた。静まり返えったこの場の無音にも掻き消されてしまいそうな細い声だ。
彼は川下勇夫。情報処理系専門学校の新卒で今年入社した社員だ。
端整な顔立ちにも後押しされて、期待の新人と謳われていたのも今や懐かしい。PCを相手にした仕事は熟せるのだが。こと人間関係の絡んだ物事への要領が悪い。実際、彼のところで重要な連絡事項が止まり、作業が滞ったことは一度や二度ではない。最近ではむしろその顔立ちの良さが祟り、劣等感を覚える――リーダーみたいな――やからに失敗をあげつらわれて、時にこのような吊し上げとも言える仕打ちを受けていた。
「〝すいません〟〝申し訳ありません〟〝以後、気を付けます〟それだけはこの半年でしっかり覚えたみたいだねぇ――」
まずい!!
「リーダー!」
繕明はドリップ中の珈琲を残して足早にタイルカーペットを踏みだした。
今日のお怒りはこれまでとは違う。何か取り返しのつかない言葉まで飛び出してきそうな、そんな雰囲気があった。勤め先でパワハラ騒動が起きるなんて考えたくもない。
「なんだ、揃江」
こちらに飛び火した怒りの形相に怯んでる暇はない。
繕明はリーダーに耳打ちした。
「それ以上の暴言はコンプライアンスに触れます。彼のことはしばらく私に任せて下さい」
コンプライアンスとは要するに企業など個々の団体組織の中だけで適応される法律のようなものである。
繕明の声音の重さにリーダーは見る間に勢いを抑えていった。
「分かった、お前に任せる。でもなぁ、こいつはもう半年以上もここにいるのに仕事が飲み込めていないんだぞぉ。仕事に差しつかえないくらいにしておけよぉ。お前はうちの前線戦力なんだからなぁ」
粘着質なイントネーションでそう言い放つと、リーダーは持っていた書類を繕明に手渡した。それは、業務計画書だった。
その後、リーダーがオフィスから出て行き、ようやく職場に平穏が戻った。
「半年経ったからこそ、そろそろ助け船も出してやらないとな」
繕明が戯けた口調を聞かせると勇夫は顔を上げた。
「すいません、揃江さん」
「あまり謝るな。負け癖が付く」
「すいませ――あっ……」
世の中の全てに申し訳ないといった表情に顔を歪ませる勇夫を見て、繕明はやれやれと思った。
「今日の仕事の後は空けとけ、ちょっと飲もう。お前がそれをうざったいと思わなければだけどな」
「い――いえ、とんでもないです! そんなことありません」
「なるほど、これじゃ怒られても仕方ないな」
JR京都駅の周辺まで足を伸ばし、居酒屋の座敷席に陣取った後、リーダーから受け取った書類に目を通した繕明は独り言のように呟いた。向かいでは勇夫がしゅんと肩をなでさせている。
「おい、話し難いからここに来い」
繕明が角席をさすと勇夫は飛んで来た。これで、ちょうど90度の角度で話すことができる。視線を交わすことが少なくなるので、勇夫には問題を考える余裕ができるはずだ。 繕明はとにかく、書類の問題点を簡潔に挙げていった。
まず、何を扱うプログラムなのかが曖昧で分からない。次に設計書作成の必要有無。既存プログラムがあることには触れてはいるが、どの程度の修正が必要なのかも記載されていない。どうやら、客先で突っ込んだ質問をしないまま帰ってきてしまったらしい。
「リーダーからは確認低度の打ち合わせだと聞いていたんですが、先方に出向くとほとんど白紙の状態から打ち合わせが始まりまして――」
つまり、リーダーの悪い癖が出たというところだろう。
まったく人の腰を砕くのがうまい……。
「あの人は少し癖の強い人だから気を付けた方が良い。それでもって、複数のプロジェクトを抱えているから、手を抜けるところを見付けるのに長けてる」
勇夫の顔色に少し浮ついた兆しを感じ取った繕明は、冷や水をかける気持ちで言った。
「だからと言って、半年経ってこれでは、正直社会人としての示しが付かないってのも分かるな?」
「……はい」
まさに青菜に塩とばかりに勇夫は委縮する。
「大体、客先の対応はリーダーや俺に付いてきたこともあるんだから未経験じゃないだろう? 何を確認しているかとか、メモ取ってないのか?」
「一応ノートに――」
勇夫が胸ポケットから小さなノートを取り出した。それを見た繕明は奇妙なノスタルジーを覚えた――そうだ、読み切り付録が過剰に挟まれた児童雑誌だ。
「出っ張ってんなぁ……」
「はい?」
「なんでもない、見せてみろ」
何故か勇夫は観念したように目を瞑ってノートを手渡してきた。まるで、成人雑誌を取り上げられる思春期の子供みたいな顔だ。
繕明は手の中でそれを開いた。その拍子に何枚もの紙切れがテーブルに落ちる。おそらく、ノートが手元にない時に書き付けた物だろう。
ノートの中には、勇夫の頭の中身が文字となって明け透けに表記されていた。
何が、いつ、どこで、といった最低限の説明文はあるものの、ページをめくるごとに業務場面が変わっていて内容がつかめない。字の形は一定に整っておらず、大きさもまちまちである。その中に、繕明が教えたらしい部分の記述を見付けることもあった――他と比べて、そこだけは落ち着いた筆致で書かれている。
なんというか、その場の感情だけで文字を書き連ねたらこんな感じになるのだろうか?
はっきり言おう、全っ然まとまりがない。
これでは、思い出そうとする度に、どこに書き付けたか探さなくてはならない。
「こりゃ、飲んでられないな。川下、ヨドバシの百均に行って手帳サイズのルーズリーフとその用紙。それとメンディングテープとハサミ。あと穴開けパンチ買って来い」
「え、今からですか?」
「ここからすぐだろ? その金は俺が出す」
勇夫に千円札を握らせて送り出した後、繕明はタッチパネルでドリンクメニューを無視して適当に二品注文した。
戻って来た勇夫に指示して、ノートのページを切らせた。そして記憶を頼りに分類させる。分類したページにパンチで穴開けし、ルーズリーフにさして、メンディングテープで付箋させた。これで手製のシステム手帳の完成である。
「いいか、ただ闇雲にメモれば良いってものじゃない。やることを頭で整理して、身体で覚えなきゃ仕事は勤まらないぞ。まあ、分かりきったことを言われて苛つくかもしれないけど、それができなきゃお前、ほんとの話、職場で嫌われるぞ」
繕明の言葉の重みが堪えたのか。勇夫はその後、食事そっちのけで業務の不明点を繕明に訊ねては、その答えを熱心に書き付けていた。
オフィスの給湯ブースに芳ばしい煙が立ち上る。トップバリューの『レギュラーコーヒー』はやはり悪くない。
繕明が口に広がる苦味と香りを楽しんでいると――。
「このバカちんがぁ」
オフィスにリーダーの怒罵が響いた。
声がした方に首を巡らせる。見ると、オフィスにいる全員の視線が入り口のドアに集中していた。
「詰めが甘いんだよ。お前はぁ」
打ち合わせに行っていたリーダーと勇夫が帰ってきたところだった。リーダーは自分の管理不行き届きが露見するのを良しとしない性格で、その部分には余念がない。
さらに二、三言の小言を聞かされた勇夫は、しゅんとした顔で自分のデスクに戻った。 繕明は紙コップを置いて勇夫に歩み寄った。
「どうだった?」
勇夫は繕明に気付いて顔を上げる。
「リーダーの監視の下で再度打ち合わせに行ったんですが。最後に重要な部分の質問を忘れてまして、結局フォローしてもらいまして――」
大きな溜め息を吐いた勇夫は、先日のルーズリーフを開いて何事か書き付けると目に焼き付けるように眺める。
その様子を見た繕明は、掛ける言葉を選ばなかった。
「よくやった」
「え?」
困惑の表情を顔に貼り付けている勇夫に繕明は続ける。
「全然ダメだったのに、気がつけば間違ったところはたったの一つ。お前は十分に熟達する努力ができるってことだ。その調子で仕事の粗を消していけばいい」
「そうでしょうか……」
またぞろ溜め息を吐く勇夫の肩を軽く叩いて、繕明は声をひそめた。
「あんな奴、黙らせてやる。ってくらいの気持ちで仕事しろ。誰にも五月蝿く言われない職場環境はこの上なく快適だぞ」
勇夫の顔色に少し浮ついた兆しが見えた。繕明はこう重ねる。
「珈琲飲むか? 安物だけど、けっこういけるぞ」
「はい、頂きます」
打てば響くように答えが返ってきて、二人は連立って給湯ブースに足を向けた。