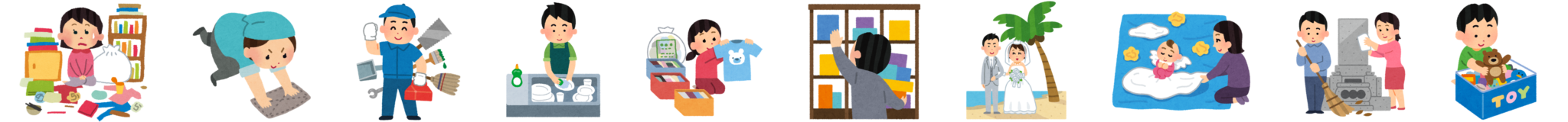日に日に寒さが増していく。山は紅がまざったまだらに色になり、京都の狭い一画にも木枯らしが吹いて顔が冷たい。
繕明は久々の連休だった。
不況とは言え、やはりIT業界は連日大忙しなわけで、最近は年末だからと立て続けに受注が入っていた。
それがようやく片付き始め、仕事納めに根詰めて失敗するのも良くないので、2連休を頂戴できたのだ。
今日はその一日目。
子供の頃と変わらず、連休初日の高揚感が胸の中で踊っていて心地良い。
近場のファミレスで朝食をすませた繕明は、気の向くままに自分の住む街を散歩していた。
戯れに入った公園のベンチに腰かけて缶コーヒーを飲んでいると、箒とちり取りを持った老齢の男性が歩いて来た。
「空き缶、ほったらかしにせんといてくれよ。公園が汚れるから」
「あ、はい」
繕明がうなづくのを確認した老人は、背中を向けて行ってしまう。見ると、箒の柄に『田向』とマジックで書いてあった。
ボランティア活動の腕章やウィンドブレーカーをしてないということは、本当に地域貢献心のある近所の人みたいだ。
缶コーヒーを飲み終えた繕明は、公園を出る時に見付けた空き缶を拾っておいた。
後で一緒にゴミ箱に捨てておこう。
日本中の人が、自分の出したゴミと一緒に、もう一つ落ちてるゴミを拾えたら、一週間後には路上にゴミなんて無くなるだろうな……。
そんなことを考えなから、繕明は空き缶用のゴミ箱を見付けて、二本の空き缶を放り込んだ。
それから、しばらく歩いていて、ちょっとした非日常と遭遇した。
どんぐりの背比べをしている一戸建てが並んだ住宅街。
その一つの玄関から、苦しそうな声が聞こえてきたのだ。
失礼を承知でも、繕明は気になって覗き込んだ。実際に事故が起こっていたら事である。
そして、ある意味かなり苦しい状況に立たされている老齢の女性と目が合った。
真っ赤な顔で首を傾げる彼女に、繕明は平謝りする。
「あ、すいません。苦しそうな声が聞こえて来たので、何事かと思いまして――」
「だったら! 手伝って欲しいんですが!」
「ああ、そうですね」
繕明は慌てて駆け寄り、彼女の手でやっと安定している和箪笥を支えた。
まだほのかに木材の香りがする――多分、桐か杉だろう。タタミ半畳ほどの箪笥だが、経年で湿気を吸っているのと金具の重さも相まってかなりの重量だった。
「ええ――っとぉ、これをどうすれば?」
どうしても震える声でそう訊くと、彼女は身も蓋もないことを口にする。
「捨てに行きたいんです」
もったいない。
繕明は正直にそう思った。
和箪笥など、手紙や刊本と同じで、近年失われつつある文化の一つである。それに、ちゃんと箪笥金具が使われている物なんて、希少価値すらあるに違いない。
繕明は我慢できなくなって一旦下ろした。
「もったいなくないですか? こんなに風情がある物なのに」
息切れしながら訊ねる。
「今の家の雰囲気には合わないんです」
彼女の答えを聞いて、なるほどと思う。
見上げた家は、実に西洋風でモダンな外観だった。内装もこれにならっているはずだ。彼女の口振りだと和室もないのかもしれない。
「それに、これはきっと昔の女の思い出があるから、あいつも捨てずにいつ迄も置いてるんだ」
「はい?」
繕明が疑問符付きの声を上げると、彼女は訊きもしないのに話し始めた。
「時々、あいつがこの箪笥の前にペタンと座り込んでは、にやついてるんだよ。考えてみれば、結婚した初めからそんなことがあったように思うんだ。
私がいい加減こんな古くさいもん捨てろって言っても、頑固一徹でこの家にまで持ち込みやがって――。ここはあいつと二人で遣り繰りして買った家なのに……」
ひとしきり話し終わったのか、彼女は相撲を取るみたいに箪笥に組み付いた。
「だから、あいつが居ない間に捨ててやるんだ!」
彼女が繕明に振り向く。
「さあ、手伝って」
なんだか、悪事の片棒を担がされているような気がしたが、〝乗りかかった船〟という言葉もあるし、繕明は取りあえずもう一度持ち上げた。
その時、箪笥の中でカサカサと紙の擦れあう音がした。
「なにか入ってますよ?」
「いいえ、全部出しました」
一刻も早く捨てたいらしく、押し手の彼女は繕明を急かす。
でも、繕明が力を抜けば下ろさないわけにはいかない。
「物が入ってたら、迂闊(うかつ)に捨てられませんよ」
石畳の上に置いた箪笥を開けてみる。彼女が不満そうな目で見てくる。でも、これほどの入れ物だ、おのずと中身にも敬意を払いたくなるのは人情だろう。
上から引き出しを開けていた繕明は奇妙なことに気付いた。一つの引き出しだけ、底が浅く造られている。
引き出しを箪笥から引き抜くと、一番奥に指が入るくらいの穴があった。
二重底――からくり箪笥か!
先人達がプライベートを守るために――ことに大切な物をしまうために――編み出した知恵だ。
思わず開いた引き出しの秘所の中には――。
数枚の便せんが入っていた。
〝相生早苗さんへ 僕は田向善太郎と申します――〟
このくだりから始まる文章の展開を予想した繕明は、そこで目を止めて彼女に手渡した。
彼女が受け取ったあとになって、誰へ向けての手紙か知らないことに気付く。ひょっとしたらこれが切っ掛けで、一つの破局を起こしてしまうかもしれないと、やにわに心配になった。
彼女の一挙手一投足を、繕明が緊張して見守っていると、
「これ、私に宛てて書いてる……」
顔を赤らめた彼女が早苗だったようだ。
「そう言えば、こんなの貰ったことなかったわ。あいつ、口下手なりにもちゃんと言ってきたから」
便せんの全てに目を通した早苗は、それを大事そうに引き出しへとしまう。
そして、真っ直ぐこちらに向き直った。
「戻すの手伝って」
慣れない力仕事で痛んだ肩と腰をさすりながら繕明は歩いていた。
すると、道の向こうからさっき公園で会った老人が歩いて来る。手には集めたゴミが入っているゴミ袋とちり取り――そして、柄に『田向』と書かれた箒。
あの家の表札と同じ苗字だ。
その厳格そうな顔立ちに、便せんに書かれていた几帳面な筆はこびの字が綺麗に重なる。
「なんだ、俺の顔に面白いもんでも付いてるのか?」
すれ違いざま、知らず目が吸い寄せられていたその顔が渋面で振り向いた。
「いえ、すいません。お幸せに――」
「ああ? なんだそりゃあ?」
にわかに早足になって行ってしまう老人の背中を見送ったあと、繕明は休日の散歩に戻った。
見上げた空は蒼く透きとおっていて、いくつかの冬らしい薄雲が飾られたように浮いている。
「今日は良い天気だなぁ~」