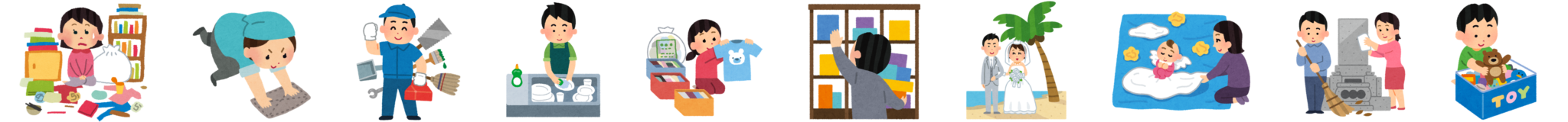頭の中がぐちゃぐちゃだ……。
木本香奈は机に鼻をくっつけて頭を抱えていた。
本当はすぐにでも泣き出したい。そんな気持ちだけが胸の内で煮詰まっていく。
顔を上げて目の前の勉強机を見た。
数学のチャート式。理科と英語の参考書。大学試験の過去問題集。リスニングとライティングのためのMP3プレーヤーとスピーカー。キッチンタイマーのアプリを120分に設定したスマートフォン。散らばった解答用紙――中には破った用紙もある。各教科のノート。
まるでお祭りの賑やかしみたいだ。
散らかりまくった机の上を見た香奈は、この心の〝ざわつき〟はきっとこんな形をしているんだと思えて苦笑いした。
大学受験。
18歳を数えた香奈の両肩に、そんな人生を左右するシンボリックな言葉が、重くのし掛かっていた。
滑り止めは難なく越えられた。けれども、本命の大学を受験するという緊張感は、今まで感じたことのないほど大きなモノだった。
それに動揺した心に、不安から化けた恐怖がどっしりと居座っている。
もし、落ちたらどうしよう……。
妥協して滑り止めの大学に通うのかな?
それとも浪人?
また来年受けるの?
それでも受からなかったら?
就職? アルバイト? フリーター? ニート?
私にはやりたいことがある。なりたいモノもある。
でも、それって本当にそうなのかな?
私はどうなりたいのかな?
来月に控えた一次試験まであと10日を切っているのに――。
最後の追い込みを掛けなきゃならないのに――。
――――。
ふっ、と香奈の思考が途切れた。身体の内側にあった〝ざわつき〟が急に身を潜める。
部屋の無音は耳に入ってくる。
なのに……。
「……なんにも頭に入ってこない」
香奈は机に鼻をくっつけて頭を抱えた。
思わず鼻をクスンッと鳴らしてしまう。
それでも、涙だけは我慢した。泣いてしまったら、なにかに負けてしまう気がした。
ふいに好きなアーティストの歌が聞こえた。
君は門出に立っている誇り高い勇者のようだ。
と歌っている。でも、今の香奈にはすべてが皮肉にしか聞こえなかった。
しばらくそうやって自分の心を自分で踏みにじっていた。
けれども、その歌が止む気配はない。
ようやく、自分のスマートフォンから鳴っていることに気がついた。
見ると通話着信。
相手は――。
「ヨシ兄?」
パネルに表示された通話ボタンを押して耳に当てる。
「もしもし、香奈ちゃん? 繕明だけど」
いつもの落ち着いた声が聞こえてきた。
「なに? どうしたの? ヨシ兄から電話してくるなんて珍しいね」
香奈は出来るだけ快活な声を彼に聞かせようと思った。少しでも気を抜いたら声が潤んでしまいそうだった。
「今、勉強中?」
「うん、真っ最中」
「そうか、そうか」
なんだかこっちの気持ちを汲んでいるような響きだったので、香奈は少しムッとした。
こんな気持ち……、分かられてたまるか!
「それで、なんなの?」
つい声を強めると、従兄弟の揃江繕明(そろえ よしあき)はなんでもないことを言うようにしゃべり始めた。
「机の上、散らかってるんじゃないかなと思ってさ。別に、教科を一つに絞ってやった方が効率が良いとか、そんな下世話なことを言うつもりじゃない。ただ――」
彼はそこで言葉を切ると、受話口の向こうから深呼吸をする様子が聞こえてきた。
そして――、
「目の前のことだけを片付ける。そう考えてほしい。ひょっとしたら、なんか無茶苦茶なことを考えてしまうかも知れないけど。今はただ、目の前のことに集中すれば良い。
俺は今まで目の前にある物だけ、鼻の先にあることだけを片付けてきた。過去や未来っていうのは、片付けようにもそこまで手が届かないからな。
知ってるだろうけど、〝こんな勉強が将来の役に立つのかよ〟っていうのが、俺の小学校の頃の口癖だった。
でも、今なら分かる。
その勉強は、たった今必要なんだ。
今現在の困難を乗り越えるために必要なんだ。そんな当たり前のことを、社会人になってから気付いた。
だから、香奈ちゃんにはその二の舞になって欲しくない」
香奈は黙ってうなづいた。そうしないと、情けない声を彼に聞かれてしまうから。
「余計なお世話だったら謝る。でも、俺もその時期を知ってるからこそ、言ってやりたいと思ったんだ」
香奈は熱い物が頬を伝っているのを感じた。
「こんなことでしか、支えになってやれないけど、合格発表の日は絶対に休みを取る。みんなで一緒に行こう」
「うん……」
ついに情けない声を出してしまった。彼に聞かれてしまった。香奈は恥ずかしさで耳の先まで熱さを感じた。
「頑張れ香奈! お医者さんになるんだろ!」
〝お医者さんになる〟
子供の頃、繕明が東京に遊びに来ては姉の愛奈と3人で遊んだ。男勝りの愛奈と繕明はやんちゃな遊びが好きで、よく二人揃って怪我をしていたものだ。
そんな二人の後ろを、香奈はいつも絆創膏と消毒液の入った手製の救急箱を持ってついて行くのだった。
いつだったか、繕明がまた怪我をしたので、香奈はいつものように傷口をティッシュで拭き、マキロンで消毒してから絆創膏を貼った。
その時、頭にフワリとなにかが乗った。
「いつもありがとう、香奈ちゃんはとっても良いお医者さんだ」
彼の手に頭を撫でられていた。
あたたかい手だった。
そのあたたかさがストンと胸まで降りてきたのだった。
香奈は笑みをあふれさせて言った。
「うん! 香奈、お医者さんになる!」
「うん! 私、頑張る!」
「ああ! 頑張れよ!」
もう、聞かれてもよかった。彼にだったら、自分のどんな情けない声を聞かれてもかまわない。
「ヨシ兄――」
香奈は潤み声で言う。
「ありがとう」
「ああ」
彼との会話が終わった。
香奈はそのまましばらく泣いて、また机に向かった。
身体の内側は、部屋と同じように静かになっていた。
目の前の机の上には片付けなければならない物がいっぱいあった。
そして、片付けられると思った。
あの〝ざわつき〟だって、涙と一緒に片付けることが出来たのだから。