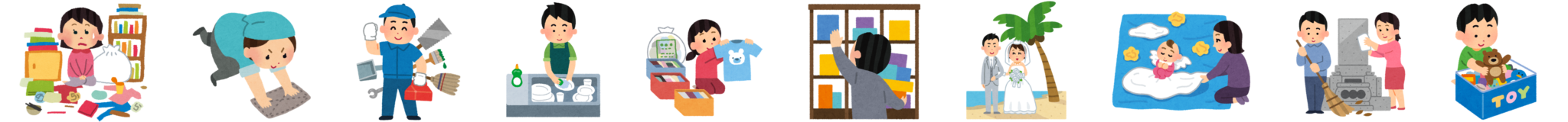「とにかく、一度来て頂けませんか? どうにも難儀しております」
2週間前に電話口で聞いた、か細い声を思い出しながら揃江繕明は京都と大阪の府境を越えた。国道を数分走った先、民家と田んぼの割合がちょうど半々の地域に、その家はあった。
車を停めて、『松戸』と書かれた表札を見てからインターフォンを押す。
「はい」
「揃江です」
「ああ、わざわざどうも」
ほどなくして、ガラス張りの引き戸がやかましい音を立てて開いた。痩せぎすだが、肩の角度がかっちりと分かる老人が出てくる。想像していたよりは若い。
「お電話した松戸忠志です。ちょうど、妻は出掛けておりますんで、今のうちに」
玄関に入ると、高い上がり框とすっきりと奥に伸びる廊下が見えた。
「お邪魔します」
通された畳敷きの居間には、真ん中に四角い卓袱台がひとつ。その脇の茶箪笥には、急須や食器の他に、洋酒とグラスが飾られるように収まっている。
「ああ、何か飲まれますか?」
「いいえ、それより問題の場所に行きましょう」
忠志がうなづいたあと、奥の襖が開けられる。仏間だ。壁に掛けてある数枚の遺影からは、厳粛な視線が注がれているようで無意識に背筋を伸ばし直してしまう。
「こちらなんですが――」
言いながら忠志は仏壇の隣にある納戸を手差した。
「開けても?」
繕明の質問に忠志がうなづく。戸が「きぃ~」と窮屈な音を立てて開いた。と共に足元を〝黒い物体〟がササッと横切った。
「ああ! まただ!」
そう言うや否や、忠志は手近にあったティッシュを数枚引き抜いて重ね持ち、慣れた手つきで〝それ〟を捕まえた。
「ったく、どっから入った!?」
忠志は手の中で触覚をひょいひょいと動かしている〝それ〟に向かって悪ガキを叱りつける声で言う。
繕明は納戸の中に目を戻した。
「これはまた随分と出っ張ってますね」
「はっ?」
繕明のこぼした言葉に忠志が頓狂な声を上げたので、繕明は声の調子を戻す。
「もう、これ以上は入りませんね」
「え、ええ、そうなんですよ」
寿司詰め状態とはよくいったもので、この納戸の中はまさにそれだった。掃除機、ヒーター、扇風機、ちらっと電子レンジらしき物が覗いてたりもしている。あとはその隙間を埋めるように――ここからはいちいち『大量の』と頭につけることになる――各種洗濯用ハンガー、ぬいぐるみ、人形、傘、服、食器類……などなど。よくここまで詰め込んだものだ。
「上からいきましょう。これだけきちきちに詰まっていると、崩れてくる危険性もありますから」
「やってくれますか!」
縁側のサッシ戸から〝それ〟を放り出していた忠志が明るい顔で振り返った。
「いやぁ、よかった。一人だとどうにも不精してしまうもんでして、助かります」
庭にビニールシートを広げ、その上に納戸の中身を並べていった。
掃除機、温風式ヒーター、電子レンジ。
「私ら夫婦は、七年前一緒に定年を迎えましてねぇ。これは、二年くらい前から始まったもんで。妻のやつ、何だか新しい物を買おうとすると嫌がるんですわ」
トースター、電気ポット、液晶テレビ、炊飯器。
「でも、古くなった物って性能も落ちてくるし、電気代も馬鹿にならんでしょう?」
洗濯用ハンガー(大量の)、傘(大量の)
「それで、買い換えようとすると、妻の奴が古い物を全部この納戸中にしもうてしまうんです」
ぬいぐるみ(大量の)、人形(大量の)。
「おかげで納戸に物がしまえへんし、最近じゃあ、どっからか拾ってくるようにまでなりましてねぇ――」
「全部まだまだ使える物ばかりですね」
繕明はぼそりと言った。
「はい?」
「いえ、量が多いですね」
「ええ、困ったもんでしょう?」
忠志は溜め息まじりに言う。ぬいぐるみや人形はともかく、出てきた家電に関しては数年前に最新型としてテレビCMされていた物まであった。
「これ全部、本当にもういらないんですか?」
「ええ、洗濯機は乾燥機能付きのがありますからハンガーはいりませんし、他のも全部買い換えましたから」
「じゃあ、どうするんです?」
「そうですねぇ、ちょうどええですし、業者に来てもらって処分してもらいましょうかね」
忠志は携帯電話に向かって、「周辺の回収業者」と言った。
小気味の好い電子音が鳴り響き、機械的な女声で、「2件あります」と告げられるのが聞こえた時――。
繕明は納戸の最奥に小さな箱があることに気づいた。
蓋を開けてみると透明なビー玉が5個並んでいる。
「ご主人、これは?」
それを持って縁側に出ると、忠志が首を伸ばして箱をのぞき込んだ。
「さぁ、またあいつがどっからか拾って来たんでしょう」
「あんた、なにしてんの!?」
悲鳴にも似た声に振り向くと、忠志と同じ年代の女性が顔に険を帯びさて駆け寄ってきた。忠志の妻らしきその女性は、小柄な身体を揺すぶるその片手に買い物袋をさげている。
「見ての通りや、納戸の片づけしとる」
「その人は?」
彼女の目がこちらに目を移す。
「私は――こう言う者です」
繕明は名刺を取り出した。
「片づけ請負……清掃会社の人ですか?」
「いえ、趣味です。お金はそれほどいただきません。今回はガソリン代の半額で2千円です。それ以上のお金は決して受け取りませんので、どうかご心配なく」
繕明が静かな声を聞かせると、彼女も少し落ち着いた様子だった。
ふっと彼女が目を繕明の手元に落として言う。
「あ、それは――」
「好美お前なぁ、なにをこだわってゴミ集めしてるんか知らんけど、もうええやろ」
割り込んできた忠志の苛立った物言いを聞いた好美は、信じられないといった顔、いや裏切られたといった顔をした。ぐっと唇を結んだかと思うと、繕明から箱を取り上げて背中を向け、足早に家の裏に行ってしまった。
「あ、あの、ご主人――」
「放っといたらいいんですわ」
こちらを見もせずに忠志は電話をかけ始めている。
箱のことが気になった繕明は、我知らず好美のあとを追った。
家の裏は家庭菜園になっていたが、夏しか使っていないらしく、キュウリらしき蔓が干涸らびている。好美は勝手口の前で、折りたたみの椅子で背中を丸めていた。
箱の中のビー玉を指先で数えるように右端から左端に移している。繕明をちらりと見やってから好美はビー玉に目を戻した。
「あの人ね」
言い分けを重ねるように声で好美は続ける。
「定年したら毎日子供の頃みたいに暮らそうって言ってたの」
2つ目のビー玉が左側に移る。
「だから、子供らがしっかりしてからはウチもパートで働き始めて、あの人と頑張ってお金貯めたんよ」
3つ目のビー玉が左側に移る。
「待ちに待った定年が来て、子供らも「お疲れ様」って祝うてくれて、あの人と二人で楽しい毎日が始まったわ」
4つ目のビー玉が左側に移る。
「毎日二人で散歩に行って、馴染みの喫茶店でお茶したり、春はお花見、夏にはお祭り……。あの人、男伊達らに炭酸が苦手でねぇ。ウチがラムネ飲もう言うても、結局ウチだけが飲むねん」
5つ目のビー玉が左側に移った。
「でも、それも4年目まで。5年目にはあの人、おもて出るのん面倒臭がるようになってな。まだまだ足も達者に動けるって言うのに……。その年のお祭りは、ウチが無理矢理連れ出したんや。それが癪に障ったみたいで、もうそれっきり……。その頃から消費癖が始まって、まだ使えるのに――あとは捨てるだけになってしまった物が、なんや可哀想に見えてもうて……」
好美は箱の蓋を閉じ、長くゆっくりと息を吐いた。
なるほど。
得心いった繕明は口を開いた。
「ご主人にそのことを伝えてないんですか?」
「気ぃついて欲しい。っていうのが女の心情や。男には分からんか?」
「でしたら提案があります」