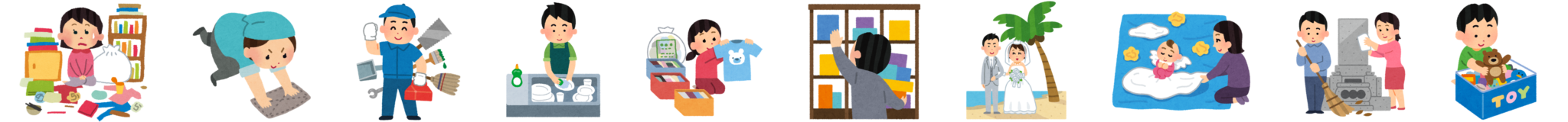「ご主人、ちょっと待って下さい」
携帯電話で話し込んでいる忠志を繕明は呼び止めた。
「奥さんが自分で片づけたいと言っているんですが」
電話を耳から外して、忠志は責めるような目で彼女を見据える。好美がくさくさした様子で言う。
「ウチがやったことやからな……」
「どないする気やねん?」
「配ろうかな思て」
好美の言葉に、呆気に取られた顔をする忠志に構わず、繕明は家電の動作確認を始めた。「どれもこれも、まだまだ元気に動きますね」
「せやったら、買い取ってもらったらええんやないですか?」
「個人の回収業なんて、出張費だなんだと理由つけて買い叩かれるのが落ちですよ。ここのあるもの全部セットでも2、3千円。あるいは無料回収でしょうね。リサイクル店でも大して変わらないと思います。だったら、地域貢献しましょうよ」
「そんなことしとったら日が暮れてしまいますわ」
「まあまあ、余暇の楽しみだと思って――」
繕明に言ってすかされた忠志は車を出してくれた。
松戸夫妻の乗った車に繕明は言った。
「それじゃ、そちらはお願いします」
「あんたそんなに一人で配れるんのか?」
繕明の車には、炊飯器、掃除機、温風式ヒーター、トースター、それに大量の傘が詰め込まれていた。
「ええ、あてがあるんですよ」
二人の車とは反対方向に向かった繕明は、適当に停めてスマートフォンを操作する。
賃貸物件の紹介サイトを開いた。目当てはここ周辺のワンルームマンションだ。そこなら一人暮しが多い上に、その大半が学生である場合がほとんど――中古の家電が宝物に見える時期でもある。
条件を入力して検索にかけると、一気に12件も引っかかった。
しめしめっと。
思わずニヤリとしてハンドルを握り直すと、繕明はハンドブレーキを戻した。
掃除機や調理器具というのは、やはり必要性が高いらしい。一人暮しの皆々様は「タダならば」と目の色を変えて引き取ってくれた。傘は近くの駅に、雨の日の貸し出し用として全部配り終わった。
しかし、ヒーターだけ残ってしまった。まあ、仕方がないといえば仕方がない。生活環境の最優先と言えば、やはり室温なのだ。そこはしっかりと揃えられていた。
「もらってもしょうがないし。こうなったら一軒一軒、インターホン押してみるか」
目についた一軒家の前に車を停めて、インターホンを押す。すぐ返事がきた。
「はい」
「すいません、私、揃江と申しますが。今日、家の片づけをしてたら、まだまだ使えるヒーターが出てきたんですけど、よろしかったらもらって頂けないかなぁ、と思って――」
少し沈黙がおりる。
これは、さっき行ったいくつかのワンルームマンションでも同じだった。やはり、こういうことを申し出てくる手合いは警戒されるようだ。
「はあ、それは引き取って欲しいってことですか?」
「はい、そうなんです」
「タダでですか?」
「はい」
「う~ん、ちょっと見せてもらえます」
苦肉の策は承知の上だったが、十数件まわって全てのお宅でいらないと言われるとは思わなかった。その分名刺は配れたが……。
それなりに「温風式だから火事にもなりにくい」と、セールスポイントを挙げてはみたものの、はっきり言って梨のつぶてだった。ガスファンヒーターには敵わない。
松戸夫妻に「あてがある」と豪語したのだから、配りきってしまいたい。だが、気づけばもう陽が傾きかけていた。
「うちの地元なら、もらってくれる人がいるかものなぁ」
と、弱音が出てしまった。途端に好美との約束を思い出して繕明は頭を振る。
「ダメだ、ダメだ」
今日中に配り終えるんだ。一つでも残ると、好美が忠志に聞かせる台詞の精神的な意味がぼやけてくる。
赤みが差し始めた空に焦りを感じていると、小さな商店が目に入った。
「ちょっと、頭冷やすか……」
道の端に車を停めて、繕明は店に入った。どうやら元は駄菓子屋だったらしい。今は地域に支えられている個人商店のようだ。
店内の野菜は『近くの畑で収穫されました』と看板が下がっている。陳列されている袋菓子などの食品類、洗濯用洗剤や石鹸などの生活用雑貨も、古き良き店独特の雰囲気を帯びているようで、なんだか見た目に味がある。
「いらっしゃい」
番台に座るおばあさんが腰を上げた。
「なにを差し上げましょう?」
「缶コーヒーはありますか?」
「冷たいのでええんならそっちの棚――」
言いつつおばあさんが指さした方に繕明は歩を進めた。年式の古いドリンククーラーがあった。
そして、繕明は別の商品に目を止めた。
「これはお幾らですか?」
「それはこないだの売れ残りやから五十円」
そこで繕明はおばあさんに顔をまじまじと見られていることに気づいた。
「なにか?」
「いやね、この辺では見かけへん人やし。こんな小汚い店に来るには小綺麗やなって思うたから」
「いやぁ、まぁ、ふらっと来たって感じでして」
「この店に来るんは近所の人らばっかりでねぇ――」
話し好きなおばあさんだった。
繕明の人当たりの良さに警戒心を解いたのか、他人なら構わないと思ったのか、かなり砕けた話題が飛び出してきて、それが二転三転する。
「それにしても、そろそろこの時間は冷えてきたねぇ」
ふと言われたことに外を見やると、空が紅くなっていきていた。
「この店、夏は風が抜けるさかい、勝手がええんやけど。この時期になると床がコンクリ剥き出しやからかなぁ、靴まで底冷えするみたいやねん」
それを聞いて繕明はピンときた。
「暖房器具がないんですか?」
「ないんよ。あたしは足悪いし、車もよう乗らんから買いにも行けんしなぁ」
繕明はにんまりと笑った。
「でしたら――」
繕明が松戸宅に戻ると、二人もちょうど帰ってきた。
「ほう、ほんまに全部配りはったんかいな」
「ええ、首尾良くいきましたよ」
「そうかいな。ああ、えらぁ……。やっぱり年やな、ちょっと動いたら腰が痛なるわ」
そう言う忠志の隣で、好美は哀しそうに顔を翳らせた。それから、訴えかけるような目を繕明に向けてくる。
繕明は好美に笑い返した。その顔を今度は忠志に向けて名刺の束を取り出した。
「ご主人、それだけの価値はあると思いますよ」
それを裏向けて差し出す。受け取った忠志は一枚ずつ目を通していった。
『松戸さん 掃除機 ありがとうございます』
『炊飯器本当に助かりました やっとお米が食べれます』
『トースター ありがとう』
『ヒーターをいただきました これで足が寒くないです 大切に使わしてもらいます』
忠志は息をついて繕明に目を戻した。
「買い取りなんかよりは、よっぽど人に喜ばれてますよ」
買った物より、もらった物の方が人は大切にするものだ。好美もそれならと納得して、繕明に今回のことをまかせてくれたのである。
「まだまだ使えるんやから、ちゃんと使ったらんと物も可哀想やろ?」
好美が忠志を見上げて口を開いた。
「まあ、せやな」
忠志は言いくるめられた子供みたいな微妙な顔をする。
「ところで――」
繕明はさっきの店で買った物をポケットから取り出した。
「労働のあとの炭酸飲料はけっこういけますよ」
二本のラムネを見た忠志は目をしばたたかせた。その視線を好美の方に移す。好美も予想外のことに目を丸くしていた。
「どうですか?」
すすめる繕明に、忠志は挑むような目を向けると、水色の一本を取り上げた。「ぱしゅっ」と夏の音が響き、飲み口から泡が溢れる。
忠志は一口飲んでむせ込んだ。その後、一息に瓶の中身を空にした。
「あ゛あ゛ぁ、胸が――」
唸りながら「どん、どん」と胸を叩く。
忠志のその姿を見た好美も、口元をほころばせて繕明の手から残りの一本を受け取る。
「こんなもんはなぁ、祭りの時にでもお前が飲んどったらええんじゃ」
「そやね」
空になった瓶の飲み口を捻った忠志は、ビー玉を取り出して好美に渡した。
「あの、箱ん中に入れとけ。来年は八つになるやろ」
「そうするわ」
頭をばりばりと掻きながら忠志が家に入っていく。好美も瓶を空にしてビー玉を取り出すと、持っていた箱の中に入れた。
箱の中では、七つになったビー玉が軽やかな音を立ててぶつかり合った。
「それじゃ、私はこれで」
「うん、ありがとうね」
好美に見送られながら繕明は車を国道に向けて発進させた。道を曲がって見えなくなるまで、ルームミラーには好美の手を振る姿があった。
少しして車が国道の流れに乗った頃、
「あ! 報酬もらうの忘れた」
自分の失敗に苦笑いしながら、繕明はドリンクホルダーに置いておいたラムネを一口飲んだ。